一 向 庵
変異原性試験の発足の思い出
化学物質安全性評価コンサルタント(医学博士)石館 基
はじめに
昭和47年、私は大塚にあった癌研究所の化学療法部から、元厚生省国立衛生試験所(衛研)の薬品病理部に移ることになった。当時、癌研の所長であった有名な吉田富三博士は、化学物質による発がん実験で、世界的に知られ、若くして文化勲章を受けられた病理学者であるが、ある日、先生は私を所長室に呼び出し、直立不動の私に次のように言われた。「君、研究もよいが、ある歳になったら、自分の研究を世の中のために役立たせることを考えなくてはだめだよ。世田谷にある国立衛生試験所の小田島成和部長(先生の一番弟子の一人)から連絡が来て、細胞病理学を専攻する者が欲しいと言っている。どうかね、行かないか」と。私は、当時、その衛研をよく知らなかったのだが、確かに研究を10年以上も続けて、論文の数は増えたが、その内容が実際に人のために役立つのだろうか、甚だ疑問であった。そこで、早速先生のお勧めに従ったのである。
吉田先生は、がんの化学療法を理想と考えておられたが、治療よりもむしろ、発がん性の機構に強い関心を持っておられた。考えてみれば、がんの治療法が如何に進歩しても、がんが次から次へ発生して来るとすれば、何時までもがんの問題は解決されない。その頃、がんの化学療法はやや下火となり、それに代わって、免疫療法の可能性が問題となっていた。メルボルン大学に留学した私もがんの免疫療法に期待を持っていた。しかし、がんは一向に治らない。私は考えた。がんの発生を抑えない限り、がんの治療は所詮追いかけっこになってしまう。治療は医者に任せるとして、まず、がんの予防を研究のテーマとすべきであると。当時、衛研の薬品病理部では、色々なニトロソ尿素系の薬剤をラットに与えて白血病を誘発する研究を行っていた。興味あることに、同じニトロソ尿素でも、アルキル基の違いによって、発生する白血病の種類が違ってくるのである。私は、それ以来、化学構造と発がん性との関連性に関心を抱くようになった。
昭和49年、わが国で食品添加物として使用されていたフリルフラマイド(AF-2)注)に発がん性のあることが分かった。この物質は、非常に低濃度で、ヒトリンパ球に対して染色体異常を引き起こし、また、微生物に対してDNA傷害および遺伝子突然変異を誘発することが分かっていた。
小田島部長から与えられた私の仕事は、動物発がん試験の前に、簡単な試験系で、発がん性を予測できるような短期スクリーニング試験法の開発であった。当時、中曽根内閣対がん10ヵ年計画のもとで、厚生省では、そのための研究班が結成された。まず行うべきことは、既知の発がん性物質を片端から、色々な試験法を使ってテストすることである。国立がんセンター、国立遺伝学研究所をはじめ、各大学から多くの研究者が参加した。米国では、カリフォルニヤ大学のAmes教授らの手で、サルモネラ(ネズミチフス菌)を用いる、復帰突然変異試験(所謂エームス試験)が開発されていたが、この試験では、発がん性物質の大半が陽性になるという。わが国でもその有用性について、検討が加えられた。菌株の改良、プレインキュベーションの導入などが取り入れられた。
さて、衛研に、新たに安全性生物試験研究センターが設立され、生物部門の一つとして変異原性部が新設された。
当時の池田良雄センター長および小田島部長の推薦を受け、私が初代の部長を引き受けることになった。昭和53年のことである。初め、微生物研究と細胞研究室、後に細胞バンクなどが発足した。
本紙では、それらの経緯について、順を追って、思い出話しとして書かせてもらうことにする。
注)フリルフラマイド(AF-2)
食中毒を起こす細菌であるボツリヌス菌に有効なニトロフラン系化合物として合成され、食品保存剤(防腐剤)として当時、魚肉ハムやソーセージを常温で長期保存するために使用された。
後にはちくわやかまぼこにも使用され、当時の経済流通革命の波に乗り、スーパーマーケットを通じて一般消費者に大量に出回った。製造販売中止までの9年間に15トンが消費されたと考えられている。
Ⅰ.試験法開発の時代
まず、発がん性のある化合物と、それらと化学構造は似ているが、発がん性がないと思われる化合物について、比較検討がなされた。次に、毎年、20種以上の生活関連物質を取り上げ、細菌あるいは培養細胞を用いる変異原性試験を実施し、そこで、特に、重要と思われる品目について、実際にマウスおよびラットを用いる長期発がん性試験が実施された。時期を同じくして、国際協力事業も発足した。特に、WHOのIARCあるいは IPCSの研究グループによって、試験法の吟味が始まった。これらの業績は下記の文書に記載されているので、参考にされたい。
- Odashima S., Co-operative programme on long-term assays for carcinogenicity in Japan. Molecular and Cellular Aspects of Carcinogen Screening Tests, IARC Sci., Pub., 27, 315-322
- Kawachi T., et al. (1980), Results of recent studies on the relevance of various short-term screening tests in Japan. The Predictive Value of Short-Term Screening Tests in Carcinogenicity Evaluation (G.M. Williams et al., eds), Elsevier/North Holland Biomedical, 253-267
- Ashby J., et al. (1985), Report of the International Programme on Chemical Safety’s collaborative study on in vitro assays. Progress in Mutation Res., 5., Elsevier, Amsterdam.
さて、これらの共同研究によって、最も、発がん性と関連性を示した試験系は、細菌を用いるDNA修復試験、遺伝子突然変異試験、並びに、培養細胞を用いる染色体異常試験であった。しかし、これらの試験のいずれかで陽性を示した物質について、さらにマウスの小核試験を実施すると、必ずしも陽性とはならない。また、長期動物実験で発がん性か認められるとは限らない。品目に限りはあるが、定性的に変異原性があっても、その約25%が陽性となるに過ぎなかった。例えば、カフェインあるいは亜塩素酸ナトリウムには、それぞれ染色体異常あるいは細菌に対する突然変異性、マウス小核試験で陽性となったが、発がん性は見られなかった。従って、大部分の既知発がん性物質には、変異原性があるが、逆に変異原性物質(変異原)には、必ずしも発がん性があるとは言えないことになる。発がん性は色々な段階を経て発症する長期の事象であることを考慮すれば、むしろ当然のことであろう。物質によって生体内で活性化されるものもあれば、逆に代謝にとって解毒されてしまうものもあるからである。従って、単に、変異原性と発がん性の有無を定性的に直接比較するとことには無理がある。英国のJ. Ashbyや米国のR.W. Tennantらによれば、変異原性と化学構造との間にある相関がみられるが、定性的には、発がん性とあまり良い相関性が見られないという。しかし、がんの集団検診と同様、簡単な変異原性試験を行うことによって、先ず疑わしい物質を選別(スクリーニング)し、更に精密検査を実施する姿勢が肝心である。図1,2は、当時のスクリーニングの結果と発がん性との関連性を定性的に比較したものである。
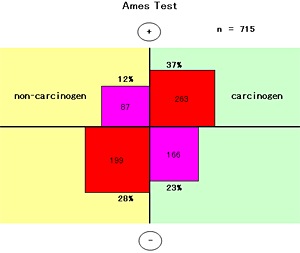 |
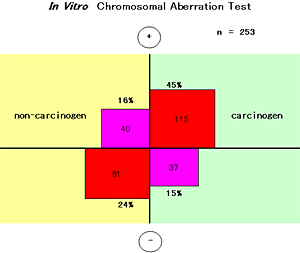 |
| 図1 Ames試験と発がん性との関連 |
図2 染色体異常試験と発がん性との関連 |
(次回に続く)
次回掲載予定
II. 試験法ガイドラインの確立
医薬品をはじめ、食品および食品添加物、農薬、化粧品、医療用の材料、その他の化学物質の安全性を確認する上で、行政的にどのような試験(遺伝毒性試験)を採用するべきかという問題は極めて重要かつ深刻な問題であった。
III. 環境変異原の検出
試験法の確立に伴い、我々の環境中には色々な変異原性物質が存在することが分かって来た。
即ち、変異原の検出の時代に入った。
最終回掲載予定
IV. 変異原性、発がん性の機構の究明
解熱鎮痛剤フェナセチンには弱いながら発がん性が認められているが、通常のAmes試験では検出されにくい。
しかし、ハムスターのS9を用いると、変異原性が発現される。
V. 変異原性試験の結果の評価
in vitro およびin vivo試験の結果を総合して、変異原性を論ずるべきだと思う。
|